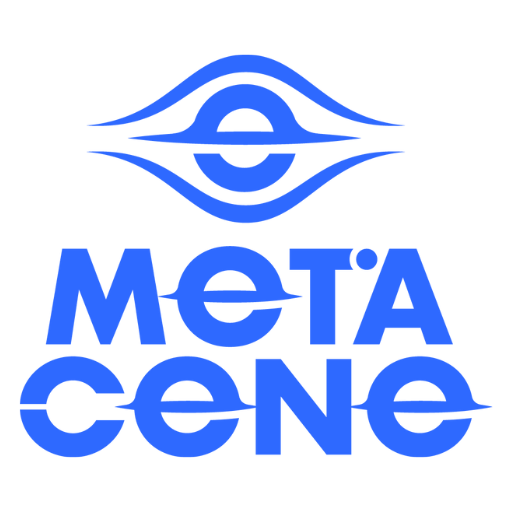(2025年1月21日 • Vivek Raman)

イーサリアムは、レイヤー2(L2)技術を活用することでスケーリングを実現してきました。L2とは、イーサリアムのセキュリティを引き継ぎつつ構築される、カスタマイズ可能なブロックチェーンです。このL2アーキテクチャにより、セキュアで分散化され、中立的なイーサリアムL1(レイヤー1)を基盤としながら、ニーズに応じた拡張性の高い環境を柔軟に構築することが可能になります。こうした仕組みによって、イーサリアムは次世代のデジタル経済の「中核インフラ」となる道を歩んでいるのです。
なぜイーサリアムは、すべてのユーザーやアプリ、流動性をレイヤー1に集約するのではなく、複数のレイヤー2(L2)ブロックチェーンのネットワークによってスケーリングする道を選んだのでしょうか?
その理由を探るには、まず「なぜブロックチェーンが存在するのか?」という原点に立ち返る必要があります
ブロックチェーンはデータベースと何が違うのか?
データベースもブロックチェーンも、取引履歴やデータといった情報を記録する仕組みである点では共通しています。ただし、決定的な違いはその「管理方法」にあります。
一般的なデータベースは、情報を一つの中央サーバーに集中的に保存し、単一の管理者(企業など)が制御します。一方、ブロックチェーンは、情報を世界中に分散したノード(コンピューター群)が相互に独立して検証しながら保存していく仕組みで、特定の誰かがコントロールすることはできません。
そのため、データベースの方が通常は速くてコストも安いのですが、ブロックチェーンにはセキュリティ性と耐障害性(=分散性)という大きな利点があります。
誰にもコントロールされないグローバルに分散された台帳であることが、高価値な資産を記録・管理する仕組みとして理想的なのです。
なぜ「ブロックチェーン技術だけ」を使えばいい、では済まないのか?ビットコインの誕生以降、よくある疑問として「暗号資産(クリプト)を使わずに、ブロックチェーン技術だけを活用できないのか?」というものがあります。
しかし実際には、ブロックチェーンと暗号資産は切り離せない関係にあります。なぜなら、ブロックチェーンは経済インセンティブ(報酬)によって成り立つシステムだからです。
ネットワーク上のノード(マイナー/バリデーター)たちは、それぞれが正直に・独立してトランザクションを検証する動機を持たなければなりません。そのため、すべてのブロックチェーンには、独自の通貨(ネイティブトークン)が存在します。この暗号資産は、ブロックチェーンの仕組みの中で自動的に発行され、マイナーやバリデーターへの報酬として支払われるのです。
ブロックチェーン・エコシステム内にネイティブ資産(暗号資産)が存在しなければ、ノード(マイナー/バリデーター)へ報酬を支払う仕組みがなくなり、彼らがネットワークの検証作業を行うインセンティブが失われます。その結果、ブロックチェーンは安全性を保つことができず、そもそも機能しません。言い換えれば、価値のあるネイティブ暗号資産を持たないブロックチェーンは、常に「データベースのほうが速くて安くて優れている」という結論になってしまいます。
ブロックチェーンのネイティブ暗号資産の価値が高ければ高いほど、マイナーやバリデーターは報酬を得るためにネットワークの維持・検証作業を行う強いインセンティブを持ちます。しかし、多くのブロックチェーンではトークンのインフレ率が高く、バリデーターへの報酬として大量に発行されることで、通貨の価値が下がってしまうなど、マネタリーポリシー(通貨設計)が脆弱です。また、ノードの数が少なく、参加のハードルが高いなど分散性が不十分なチェーンも多く、結果的に中央集権的なデータベースのように機能しているケースもあります。
ネイティブ暗号資産を持ち、かつ健全なマネタリーポリシー(通貨設計)と高い分散性(バリデーター/マイナーの自律性)を両立している主要なブロックチェーン・エコシステムは、ビットコインとイーサリアムの2つだけです。
要点をまとめると、グローバルなブロックチェーンがデータベースに対して唯一持つ優位性は、ノードやバリデーター、マイナーといった分散化されたネットワークによって、中央集権的なデータベースよりも高いセキュリティ、信頼性、耐障害性(レジリエンス)を実現できる点にあります。しかしこの利点は、文字通り「コストがかかる」という代償を伴います。つまり、ブロックチェーンはデータベースよりも遅く、そして高価になるのです。
さらに言えば、分散性が高く(=世界中の多様な参加者が自由にノードやバリデーターを運用できる状態)かつ安全なブロックチェーンであればあるほど、日常的なトランザクションにおいては処理速度が遅く、手数料も高くなるという矛盾が生じます。この現象は、「ブロックチェーン・スケーラビリティのトリレンマ」として知られており、以下の図のように整理されます:
出典:https://vitalik.eth.limo/general/2021/04/07/sharding.html
この「トリレンマ(三重苦)」は、ブロックチェーンの構造そのものに起因しています。つまり、ブロックチェーンは世界中に分散した多数のコンピューター(ノード)が連携して、トランザクションや履歴の検証・承認を行う仕組みで成り立っているためです。その結果、ブロックチェーンを設計する際には、前述の三角形(スケーラビリティ・セキュリティ・分散性)のうちすべてを同時に満たすことはできず、どれかを犠牲にする必要があります。たとえば:
- ブロックチェーンは、スケーラビリティ(拡張性)とセキュリティを両立させることはできますが、その代わりに分散性を犠牲にするケースがあります。このような場合、信頼できる運営者が存在するなら、わざわざブロックチェーンを使わずに中央集権型のデータベースを利用した方が効率的かもしれません。しかし実際には、誰でもノードやバリデーター、マイナーとしてネットワークに参加できる「分散性」こそが、ブロックチェーンにしかないセキュリティと耐障害性を生み出し、高価値な資産を安全に扱える理由となっているのです。
- ブロックチェーンは、スケーラビリティ(拡張性)と分散性を両立させることも可能ですが、その場合セキュリティが不十分になりやすくなります。こうした設計では高額な資産や重要な取引を扱うにはリスクが高く、適したユースケースとは言えません。
- あるいは、ブロックチェーンは分散性とセキュリティを優先する代わりに、スケーラビリティ(拡張性)を犠牲にするという選択肢もあります。この場合、ネットワークは信頼性が高く、安全で安定しますが、その一方で処理速度は遅く、コストもデータベースに比べて高くなるというデメリットがあります。これこそが、イーサリアムやビットコインが採用している設計方針です。
しかし、銀行や企業などの規制下にある組織は、遅くてコストの高いブロックチェーンを何億人ものユーザー向けの基盤インフラとして利用することができません。これが、ブロックチェーンの採用がいまだ本格的に加速していない大きな要因のひとつとなっています。
でも、2024年夏の時点で、ついにブロックチェーンの「トリレンマ問題」に対する解決策が登場しました!
私たちが以前の記事「ETH: キャッシュフローを持つ価値の保存手段(Store of Value)」で導き出した重要な結論のひとつは、ブロックチェーンの本質はセキュリティにあるということです。そしてこのセキュリティは、(1)攻撃に対して極めて高い経済的コストがかかる設計、(2)軽量なノードが地理的に分散してチェーンを守っていることによる分散性と非支配性、という2つの要素によって成り立っています。これら両方の条件を満たしているのは、イーサリアムとビットコインのみであり、その実現のために、彼らはレイヤー1(L1)を非常にシンプルに保つ設計を採用しているのです。その結果として、処理速度は遅く、手数料も高くなるというトレードオフが生じています。
では、もしL1(レイヤー1)自体の処理能力を上げられないのであれば、安定性とセキュリティは保ちつつも遅いL1に、どうやってスケーラビリティ(拡張性)を持たせ、ブロックチェーンのトリレンマを解決すればいいのでしょうか?
その答えは、ベースとなるレイヤー1の上に、追加のスマートコントラクト層を構築することです。イーサリアムはビットコインとは異なり、最初からプログラム可能なスマートコントラクトを前提に設計されているため、その上に構築されるスマートコントラクト層は、イーサリアムの高いセキュリティをそのまま引き継ぎながら、処理速度やスケーラビリティに特化して最適化することができます。このようなスマートコントラクト層は「レイヤー2(L2)」または「ロールアップ(rollups)」と呼ばれています。
レイヤー2(L2)エコシステムの技術的な可能性やアーキテクチャは非常に幅広く、今後の記事で詳しく解説していく予定ですが、まず理解しておくべき重要な点は、なぜイーサリアムが「ロールアップ中心」あるいは「L2中心」のロードマップを採用しているのかということです。これは、イーサリアムのレイヤー1(L1)がセキュリティと分散性に特化して最適化されている一方で、L2はそのセキュリティを継承しながら、完全にカスタマイズ可能な構造を実現できるためです。
つまり、L2の設計の自由度はほぼ無限大と言っても過言ではありません。「すべての用途に対応できる万能なブロックチェーン」は存在せず、企業、国家、個人などのユーザーは、それぞれのニーズに合わせて独自にブロックチェーンエコシステムをカスタマイズしたいと考えるでしょう。また、各国・地域ごとに異なる規制枠組みが登場する中で、ブロックチェーンもそれに対応できるように柔軟に進化していく必要があります。以下は、実際にL2で可能となる設計例です:
- 金融分野に特化した設計:銀行が必要とするのは、高速かつプライバシー保護されたL2で、ユーザーのKYC(本人確認)機能を統合したものです。こうした設計はEthereum L1には実装できませんが、銀行が独自に構築したL2であれば実現可能です。
- 将来的に不動産取引がブロックチェーン上で行われるようになると、たとえば「登記の誤り」などの法的対応により、取引の取り消しや修正が必要になる場面が想定されます。Ethereum L1上の取引は一度書き込まれると改ざんできない(不可逆)ですが、不動産専用のL2であれば、こうした巻き戻し機能を設計に組み込むことが可能です。
- ユーザーが自分自身のソーシャルグラフ(人間関係データ)を所有でき、かつ手数料が安価な設計に最適化されたL2が登場するでしょう。
- ゲーム分野ではセキュリティや分散性よりも、高速性・低コスト・互換性(ゲーム間で資産を移動できる)が重要視されます。こうしたニーズに合わせて、分散性をある程度犠牲にしたゲーム専用のL2が出てくると考えられます。
あらゆるタイプのL2は、イーサリアムのセキュリティを継承しながら、より安価で高速、さらに場合によってはプライバシー性の高いトランザクションを実現することができます。
そして、すべてのL2は最終的にイーサリアム上でトランザクションを「確定(セトル)」させるため、互いに連携・相互運用(インターオペラビリティ)が可能になります。これはつまり、すべてのL2がつながる「イーサリアム貿易ネットワーク」の構築を意味しており、それこそがイーサリアム経済圏が持つ本当の可能性なのです。
結論
L2(レイヤー2)は、スケーラビリティ・トリレンマを解決する答えであり、イーサリアムがWeb2のような中央集権的データベースに頼ることなく、数十億人規模のユーザーに対応するための仕組みです。
さらに重要なのは、L2自体がトランザクションをイーサリアムL1上で「確定(セトル)」する際に手数料を支払うことで、イーサリアム経済に価値が還元されるという点です。この手数料はETH(イーサ)に対する需要と価値を高め、結果的にイーサリアム全体の経済的セキュリティを強化します。そしてETHは、L2エコシステム全体における基軸資産(ストア・オブ・バリュー/通貨資産)としての地位をより確かなものにしていきます。
イーサリアムは、安全かつ分散化されたレイヤー1と、自由にカスタマイズ可能なレイヤー2エコシステムの両方を兼ね備えた唯一のブロックチェーンです。
ETHへの需要は、イーサリアムL1上の取引だけでなく、L2全体のユーザーとトランザクションの総体から生まれます。つまり、機関投資家にとっては「いいとこ取り」ができるのです。独自のカスタマイズ可能なL2チェーンを持ちながら、同時にイーサリアム経済圏の流動性とネットワーク効果にも接続できるのです。
イーサリアムのL2スケーリング・ロードマップこそが、スケーラビリティ、規制対応、プライバシー、高速処理、低コストをすべて実現しつつ、L1の安全性・分散性・堅牢性を最大限に保つ唯一の方法なのです。
(2025年1月21日 公開)
※本記事は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引に関するアドバイスを行うものではありません。Etherealize は、本記事に記載された情報の正確性や完全性を保証するものではありません。コモディティ(商品)への投資にはリスクが伴います。投資に関する判断を行う際は、必ず資格を有する金融アドバイザーにご相談ください。なお、Etherealize は、本記事で言及されているコモディティに経済的利害関係を持っている可能性があります。